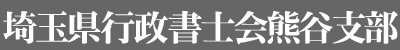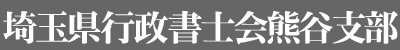個人のお客様向け業務 個人のお客様向け業務 |
| 遺言書作成 |
|
|
 遺言書作成の相談 遺言書作成の相談
『相続』を『争族』にしないために、「遺言は親の義務」です。
遺産分割をめぐるトラブルが急増している、と聞きます。背景には、相続する側の遺産に対する権利意識と期待の高まりや、不動産を思うように現金化しにくい現状などがあります。「うちは大した遺産もないから」と他人事と考えている人も多いようです。遺産規模が比較的少ないケースでもトラブルが目立つのが最近の傾向です。遺族間の骨肉の争いを避けるには、生前からの準備が重要です。「遺言は親の義務」とまでいわれております。遺言の上手な書き方や遺産の整理など、どのような事でも、行政書士事務所にご相談、お問い合わせください。
 遺言が必要な場合 遺言が必要な場合
日本公証人連合会(03-3502-8050)が作成した「遺言のしおり」では、「とくに遺言が必要な場合として具体例をあげています。
1.夫婦の間に子供がない場合。
子供がいない場合に夫が死ぬと、妻が全財産を相続できると思っている人がいますが、夫に兄弟姉妹があれば、妻の相続分は3/4で、1/4は夫の兄弟姉妹に行くことになります。この場合、夫が「全財産を妻に相続させる。」と遺言をしておくと、兄弟姉妹に限り遺留分(法定相続分の1/2か1/3)がないので、遺言どおり、全財産が妻にいくという大きな効用があります。
2.先妻の子供と後妻がいる場合。
3.長男の嫁に財産をわけてやりたい場合。
熱心に介護をしてくれた息子の妻(嫁=民法上の相続権はない。)財産を贈りたい場合。
4.内縁の妻に贈る場合。
5.相続人が全くいない場合。
遺産は、特別の事情がない限り国庫に入るが、「親しい人にあげたい。」とか「社会の福祉団体に寄付したい。」という場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
 遺言の方式 遺言の方式
遺言の方式(普通方式)
普通方式の遺言
自筆証書遺言(民法968条)
公正証書遺言(民法969条)
秘密証書遺言(民法970条)
| 普通方式遺言の長所・短所の比較 |
|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 長所 |
・簡単に作成できる。
・証人がいらないので秘密が保てる。
・費用がかからない。 |
・方式不備で無効になることがまずない。
・内容が明確。
・検認手続きが不要。
・偽造、変造、滅失のおそれがない。 |
・内容を秘密にしておくことができる。
・方式不備で無効となるおそれが少ない。 |
| 短所 |
・方式不備や内容不明確のおそれがある。
・偽造、変造、滅失の危険性がある。
・検認手続きが必要。 |
・遺言書の存在と内容を秘密にしておくことができない。
・費用がかかる。 |
・手続きが複雑。
・内容が不明確になるおそれがある。
・作成したことを秘密にしておくことはできない。
・費用がかかる。
・検認手続きが必要。 |
遺言の方式(特別の方式)
一般危急時遺言(民法976条)
伝染病隔離者遺言(民法977条)
船舶隔絶者遺言(民法978条)
難船危急時遺言(民法979条)
 法定相続分・遺留分一覧 法定相続分・遺留分一覧
| 法定相続分・遺留分一覧 |
| 相続人 |
相続分 |
遺留分 |
配偶者と
子(又は孫) |
配偶者 |
1/2 |
1/4 |
| 子(孫) |
1/2 |
1/4 |
配偶者と
父母(又は祖父母) |
配偶者 |
2/3 |
1/3 |
| 父母(祖父母) |
1/3 |
1/6 |
配偶者と
兄弟姉妹(又は甥・姪) |
配偶者 |
3/4 |
1/2 |
| 兄弟姉妹(甥・姪) |
1/4 |
なし |
| 配偶者のみ |
全部 |
1/2 |
| 子(又は孫)のみ |
全部 |
1/2 |
| 父母(又は祖父母)のみ |
全部 |
1/3 |
| 兄弟姉妹(又は甥・姪) |
全部 |
なし |
| 遺言書作成 必要資料一覧表 |
 遺言者 遺言者
1.現在戸籍謄本
2.改製原戸籍謄本
3.除籍謄本(遺言者については、出生から現在まですべて必要)
4.戸籍の附表(または住民票*本籍記載)
5.土地・家屋課税台帳兼名寄帳(写)
6.土地登記簿謄本
7.建物登記簿謄本
8.金融機関残高証明書(銀行、郵便局等)
9.株式、国債等
10.負債
11.印鑑証明書
 推定相続人 推定相続人
1.戸籍謄本
2.戸籍の附表(または、住民票 *本籍記載) |
|
 |
|
|
|